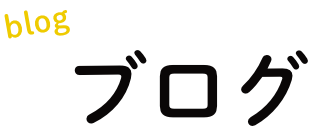楽しむ力は最強の力
楽しむ力最強説を日頃から唱えている有田ですが、「楽しい」と思うことばかりやっている
わけではありません。笑
好きなことも仕事にすると面倒なこともやらなければいけなかったり、時には苦手なことも
やらなければいけなかったりします。
サッカーの練習にしても、大好きなサッカーだけど練習は時にはしんどいこともあったり、
なかなかできないこともあったりします。
でもそんな時もそのしんどいことや難しいことを楽しめたらいいなと思います。
では、どうすれば「しんどいこと」や「難しいこと」を楽しめるのでしょうか?
まず大切なのは、「楽しもう」と思うことです。脳科学の研究では、「楽しむぞ」と意識するだ
けで、脳内にドーパミンという物質が分泌され、やる気や集中力が高まることが分かって
います。気持ちのスイッチを入れるだけで、物事の見え方は大きく変わります。
次に、楽しみ方を探す工夫です。
例えばスクールでは、練習内容は主にコーチが考えます。(今日何する?と子どもたちに
聞くことも多いですが)ですから子どもたちができるのは、「その練習をどう受け取るか」
「どこに楽しさを見つけるか」という部分です。
例えば、同じパス練習でも「どれだけ正確に出せるかを意識してみよう」と考えると、ただ
の繰り返し練習が“挑戦の場”に変わります。
ゲームの中でも「先週のゲームより 1 回でも多くボールに触ろう」と思うだけで他人と比較
することなく、自分の中で目標を持つことで楽しく充実感を得ることができます。
心理学の研究でも、「与えられた課題の中で自分なりの楽しみ方を見つけられる人」は、
意欲が長続きしやすいと言われています。つまり、練習をどう受け止めるかで、その日の
充実感は大きく変わるのです。

そして、そのものを好きになることも大切です。
「好き」という感情は、学習や記憶に深く関わる扁桃体や海馬という脳の働きを活発にしま
す。サッカーを好きになれば練習も自然に頑張れますし、勉強も「自分の好きなことにつ
ながる」と思えば、ぐっと身近に感じられます。
さらに、小さな成功体験を積むことは楽しさを強めてくれます。
「ゴールすることができた」は大きな成功体験かもしれません。でも、たとえゴールができ
なくても「今日は相手からたくさんボールが奪えた」とか「3 回パスを繋ぐことができた」とか
小さな階段を上がっていくことで楽しさは増していくものだと思います。
もちろん、失敗を恐れないことも欠かせません。
心理学では「失敗からの学び」が脳の成長に直結すると言われています。挑戦と失敗を繰
り返すことで、前頭前野という“考える力の中枢”が鍛えられ、次の挑戦に役立つのです。
だから、失敗は避けるものではなく、大切な成長の材料です。
さらに、仲間と一緒に楽しむことも力になります。
人と一緒に笑ったり挑戦したりすると、脳内にオキシトシンというホルモンが分泌され、安
心感やつながりが強くなることが分かっています。サッカーは一人ではできません。仲間
がいるからこそ、練習も試合ももっと楽しくなるのです。
そして最後に、結果よりも過程を味わうこと。
「今日は勝ったか負けたか」だけでなく、「どんなチャレンジをしたか」「どんな工夫を試せ
たか」に目を向ければ、取り組むことそのものが楽しさに変わります。結果にこだわると失
敗が怖くなります。結果よりもチャレンジした自分を褒めてあげることが大切なことだと思
います。
結局のところ、成長や上達の原動力は「楽しむこと」。楽しめる子は続けられ、続けるから
こそ強くなります。
そしてこれはサッカーだけでなく、勉強や仕事、人生すべてに通じる力だと思います。
楽しむ力は、最強の力です。
子どもたちにはこの力を大切にしてほしいし、私たち大人もまた、忘れずにいたい力だと
感じています。今月も子どもたちと一緒に楽しんでいきたいと思います。